取り組みの概要
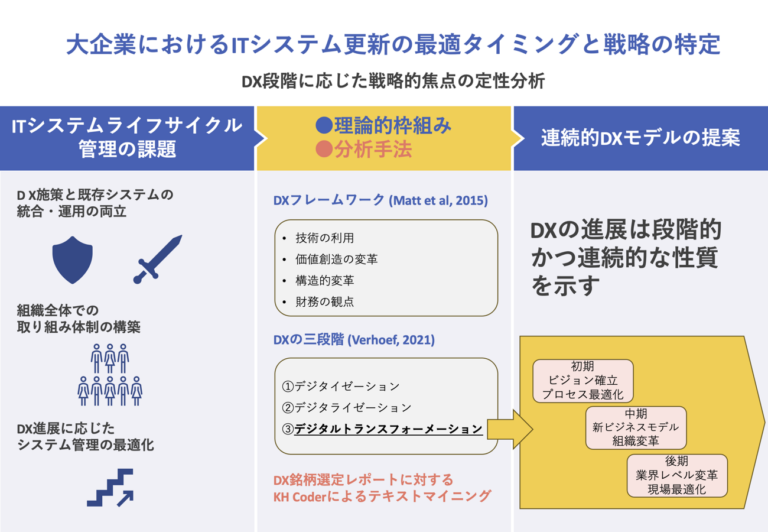
背景と課題
企業のITシステムは半世紀近い歴史を持ち、そのライフサイクル管理には以下の課題があります:
- DXの進展度合いに応じたシステム管理の最適化の必要性:企業のDX進展度によって最適な管理戦略が異なります。
- DX施策と既存システムの統合・更新の両立:革新的なDX施策と既存ITシステムの更新を同時に進める必要があります。
- 組織全体での取り組み体制の構築:DX推進には全社的な体制が不可欠です。
日本のDX推進政策では、経済産業省と東京証券取引所が共同で「DX銘柄」制度を2020年から実施しています。この制度は、企業のDX進展度を4段階(DX注目企業→DX銘柄→DXグランプリ→DXプラチナ)で評価し、投資家に対して「DXに積極的に取り組む企業」として可視化する仕組みです。これは欧米でのデジタル成熟度評価フレームワーク(GartnerのデジタルビジネスフレームワークやMITのデジタル成熟度モデルなど)と類似した取り組みですが、日本独自の認証制度として機能しています。
しかし、DX推進における戦略的焦点とDX段階の関係性の理解は十分でなく、国際的文脈における日本企業のDX分析も限られています。
私自身が経験した課題は、DXの進展段階によってシステム更新戦略が大きく異なることでした。特に金融機関との共同研究を通じて、システムの更新タイミングとDX戦略の整合性が企業の競争力に直結することを実感したことが、本研究に取り組むきっかけとなりました。
理論的枠組み
本研究では、2つの主要な理論的枠組みを用いています:
- DXフレームワーク(Matt et al., 2015)
- 技術の利用 (Use of technologies)
- 価値創造の変革 (Changes in value creation)
- 構造的変革 (Structural changes)
- 財務の観点 (Financial aspects)
- DXの三段階モデル(Verhoef, 2021)
- デジタイゼーション(紙のデジタル化)
- デジタライゼーション(ECなどビジネスプロセスのデジタル化)
- デジタルトランスフォーメーション(全社的デジタル化+ビジネスモデル転換)
研究目的
これらのフレームワークを用いた課題へのアプローチを研究目的として設定しました:
- DX段階における戦略的焦点の分析
- 国際的フレームワークの日本企業への適用可能性の検証
- DX進展パターンの評価
研究方法
使用データ
「DX銘柄2023」選定企業レポート(https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/keiei_meigara/dxstockreport-2023.pdf)
分析手法
KH Coderを用いたテキストマイニングを選択しました。理由は、数百ページに及ぶ膨大なテキストデータから客観的にパターンを抽出する必要があったためです。特に、DXという多義的な概念を扱う上で、人間の解釈バイアスを最小限に抑え、データ駆動型のアプローチでDXの段階ごとの特徴を明らかにしたいと考えました。KH Coderは日本語テキストの形態素解析と多変量解析を統合的に行える点で、本研究に最適なツールでした。
分析アプローチ
- データセット全体の分析
- 頻出語分析
- 共起ネットワーク分析
- 関連語分析
- DX区分別の分析
- 対応分析
- DX区分ごとの特徴語分析
研究における困難
研究過程では、いくつかの困難に直面しました。最も大きな課題は、DXという新しい概念に関連する専門用語の形態素解析でした。「デジタルトランスフォーメーション」「ビジネスモデル」などの複合語が適切に抽出されず、分析結果を歪める可能性がありました。この問題を解決するため、専門用語リストを作成し、強制抽出語として登録することで精度を向上させました。また、共起ネットワークの解釈においても、単なる言語的共起と戦略的関連性を区別するため、原文に立ち返る文脈確認の手順を追加しました。これにより、分析の妥当性を高めることができました。
主な発見
1. DXフレームワークに基づくデータセット全体の分析結果
レポート全体の分析では、DXフレームワークの4つの要素それぞれに対応する特徴が確認できました。
- テクノロジーの活用:デジタル技術がDX戦略の基盤として機能
- 価値創造の変革:ビジネスモデルの革新や新たなサービス開発がDXの中心
- 構造的変革:組織レベルの改革がデジタル技術によって推進
- 財務の観点:効率性向上や収益増加がDXの財務的効果として言及
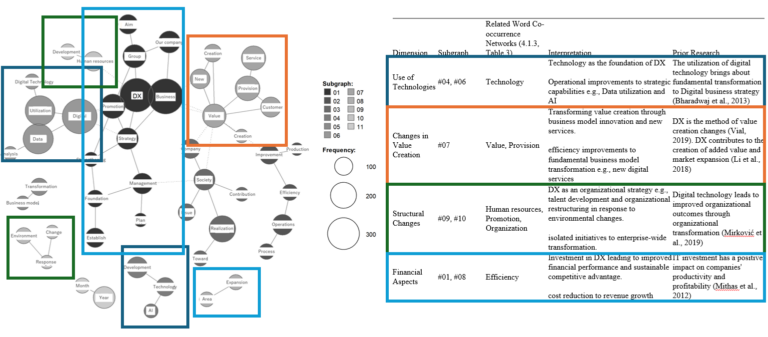
図-1 データ全体の分析:共起ネットワーク分析
2. DX区分別の分析結果・戦略的焦点
DX区分別の分析では、それぞれの区分で異なる戦略的焦点が確認されました。
- DX注目企業:継続的戦略としてのビジョン確立、物流・サプライチェーンの最適化
- DX銘柄企業:デジタル技術を活用した新たなビジネスモデル構築、組織横断的な推進体制強化
- DXグランプリ/プラチナ企業:グローバルや業界レベルでの変革、現場レベルに至るデジタル技術導入
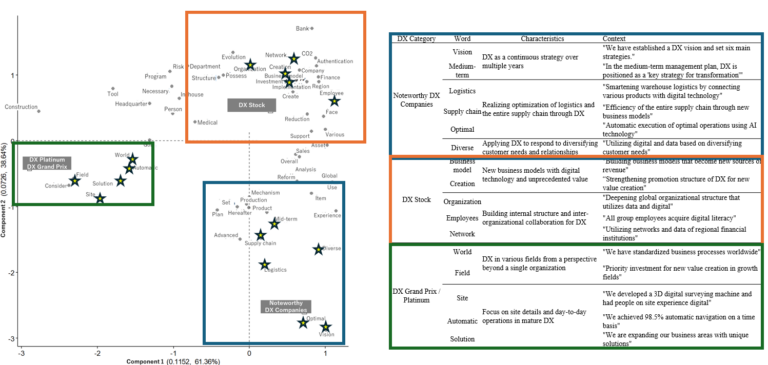
図-2 DX段階毎の分析: 対応分析
連続的DXモデルの提案
本研究では、Verhoefの3段階モデルを拡張した「連続的DXモデル」を提案しています。
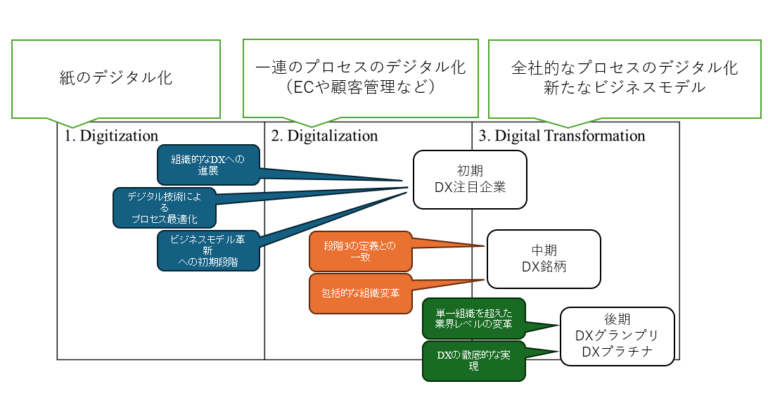
図-3 連続的DXモデル
このモデルは、DXの進展を離散的な段階ではなく連続的なスペクトラムとして捉え、「デジタルトランスフォーメーション」段階を以下の3つのサブフェーズに細分化しています:
- 初期(DX注目企業):
- デジタライゼーションからデジタルトランスフォーメーション段階への移行
- デジタル技術を活用したプロセスの最適化
- ビジネスモデル革新への初期段階
- 中間(DX銘柄企業):
- Verhoefのデジタルトランスフォーメーション段階の中核的定義に合致
- 包括的な組織変革
- 後期(DXプラチナ/グランプリ企業):
- 単一組織を超えた業界レベルの変革
- DXのエンド・ツー・エンドの実現
このモデルにより、企業は現在のDX進展位置をより精緻に理解し、次のステップに向けた戦略をより柔軟に策定できます。
実務への示唆
DX段階評価の有用性
- DXの進展度合いを客観的に評価可能
- 段階に応じた戦略的焦点の違いを特定
- 組織的対応の変化を予測可能に
システムライフサイクルへの応用
- DX段階評価を基にした更新時期の検討
- 段階に応じた組織体制の整備
- 持続可能なシステム運用への知見
結論
本研究は、DXの進展度合いに応じたITシステム更新の最適戦略を特定することを目的に、テキストマイニングによる定性分析を実施しました。分析の結果、DX段階ごとに異なる戦略的焦点が明らかになり、連続的なDX進展モデルを提案することができました。この知見は、企業のITシステムライフサイクル管理において、DX段階に応じた更新戦略の策定に寄与します。
本研究により得られた、4つの重要な発見:
- DXフレームワークは日本企業にも有効に適用できる
- DXの進展は段階的かつ連続的な性質を示す
- 戦略的焦点はDX成熟度レベルとともに進化する
- 連続的DXモデルはDX戦略の実践的な手引きとなる
これらの知見は、日本企業のDX推進において、海外の理論的枠組みを適用する際に文化的・組織的な文脈の違いを考慮することの重要性を示唆しています。また、ITシステムのライフサイクル管理においても、DX段階に応じた戦略策定と組織体制の整備に役立てることができます。
後記
この研究を通じて、私はいくつかの重要な学びを得ました。まず、DXは技術導入だけでなく、組織変革と文化の変化を伴う複雑なプロセスであることを改めて認識しました。特に日本企業では、DXを単なるIT刷新ではなく、持続的な変革として捉える視点が重要です。
研究プロセスで良かった点は、テキストマイニングという客観的手法を用いることで、先入観にとらわれない新たな知見を得られたことです。一方、課題としては、分析データが公式報告書に限定されており、企業の内部視点や実務者の生の声を十分に反映できなかった点が挙げられます。
今後は、本研究で提案した連続的DXモデルを実際の企業事例に適用し、よりきめ細かな戦略立案のフレームワークとして発展させていきたいと考えています。また、DXの各段階での具体的なシステム更新判断基準の定量化も進めたいと思います。


